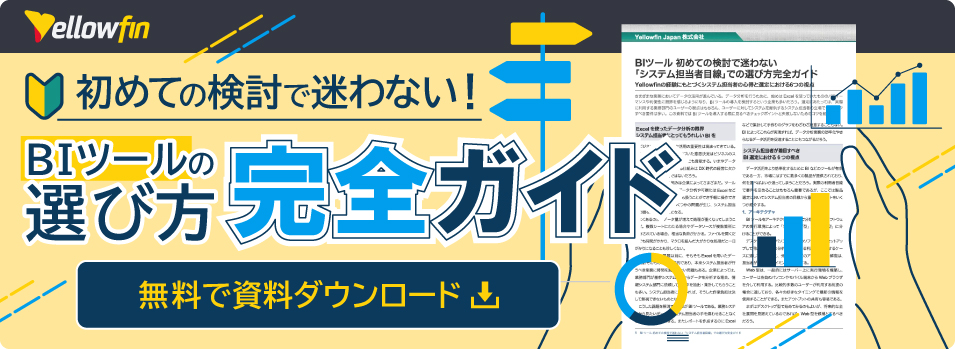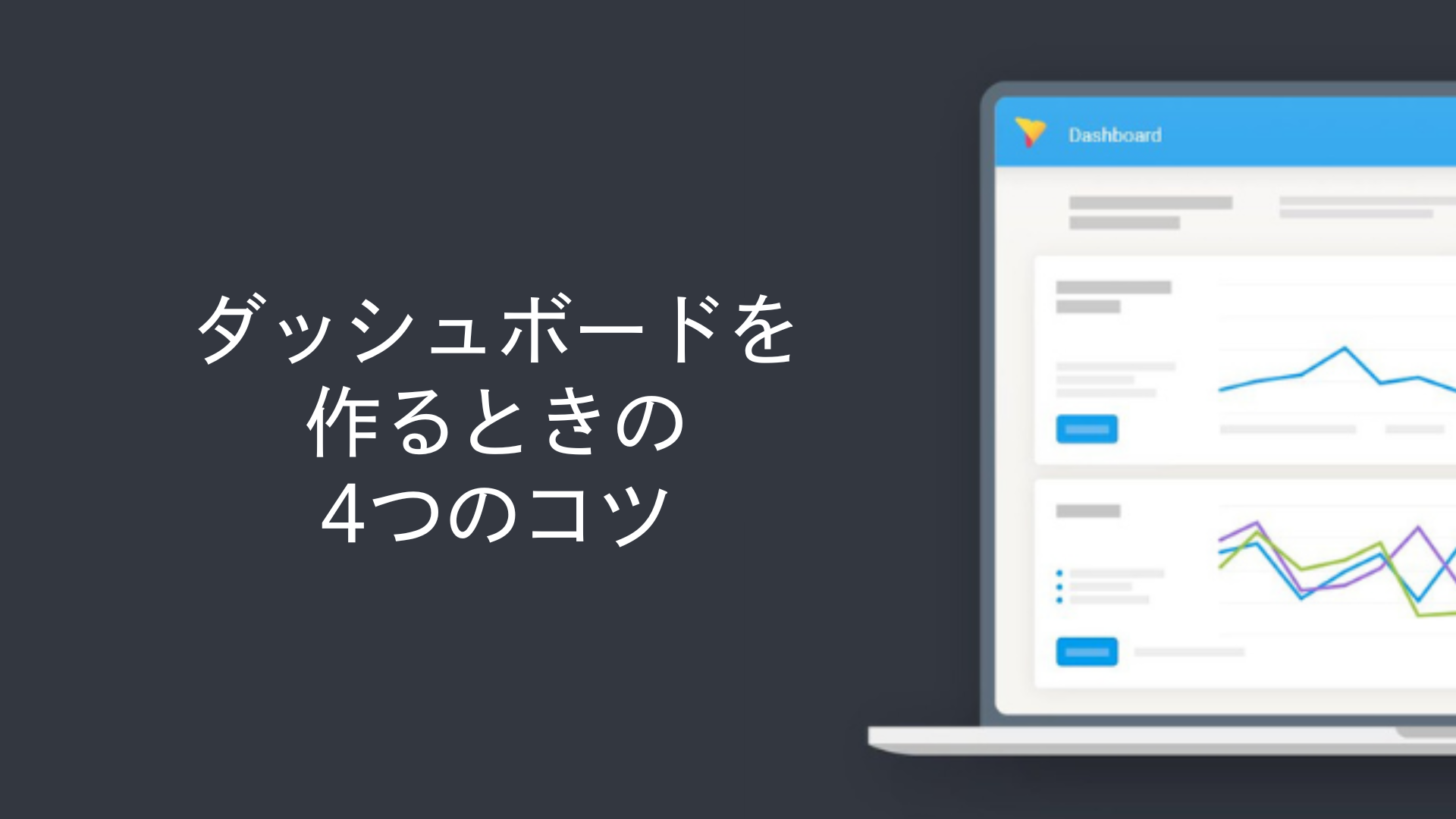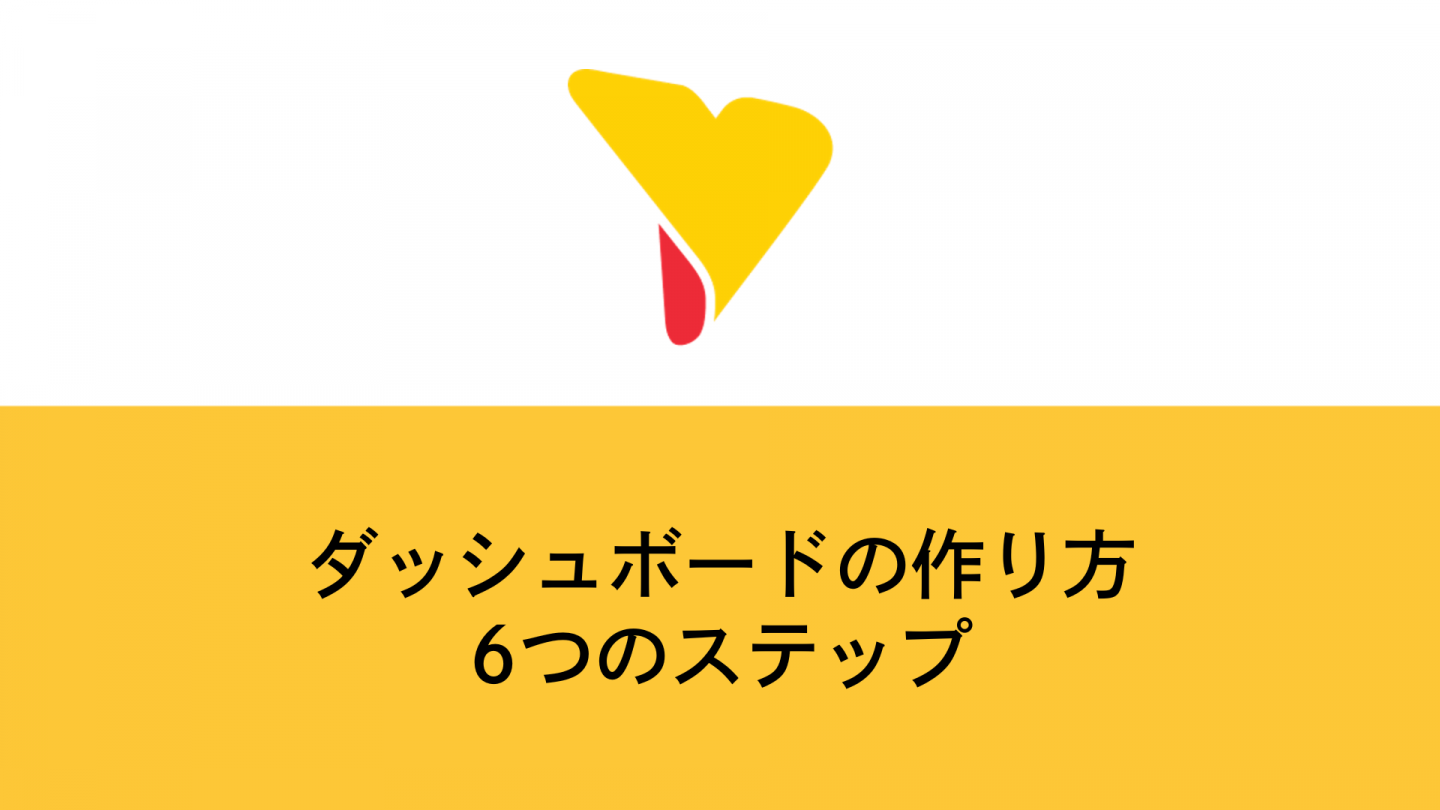
ダッシュボードの作り方6つのステップ!作成時のコツも解説
「毎回、必要なデータを探すのに時間がかかってしまう」
「複数のファイルやツールを行き来するのが面倒に感じる」
「情報がまとまっておらず、会議前の集計作業が負担になっている」
データを可視化し、必要な情報にすばやくアクセスできるダッシュボードを活用すれば、情報を一元管理できます。しかし、ダッシュボードの作成方法が分からないという方は少なくありません。
そこで本記事では、ダッシュボードの作り方と、運用のコツをわかりやすく解説します。
ダッシュボードの作り方を知る前の準備
作り始める前に、ダッシュボードの概念や基本的な機能を押さえておくことが重要です。ここでは、以下の3点について、ダッシュボードを解説します。
- ダッシュボードとは
- ダッシュボードの重要性
- ダッシュボードの基本的な機能
詳しく見ていきましょう。
ダッシュボードとは
ダッシュボードとは、売上や顧客データ、マーケティングの成果など、ビジネスに必要なさまざまな情報を1つの画面に集約し、グラフや表、分布図などで視覚的にわかりやすく表示するためのツールです。
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールと連携することで、社内に点在するデータを自動で収集・集計し、リアルタイムで更新することが可能になります。
ダッシュボードの重要性
ダッシュボードは、部門ごとのKPIや業績、顧客動向などをリアルタイムで確認でき、課題発見や戦略を見直す際に役立ちます。
データを活用するときには、複数のファイルやシステムを確認してデータを集計し、資料にまとめるという手間が必要になることも少なくありません。ダッシュボードを活用すれば、資料作成にかかる作業を効率化でき、重要な情報に素早くアクセスできます。
営業・マーケティング・財務・人事・ITなどあらゆる部門で、各部門の目標達成状況やKPI(重要業績評価指標)を共有する手段として活用されています。データドリブンな意思決定を支える、現代ビジネスに欠かせないツールと言えるでしょう。
ダッシュボードの基本的な機能
ダッシュボードを作成するときには、搭載する機能を検討することが大切です。基本的なダッシュボードの機能を、下表にまとめました。
| 機能 | 種類 |
| グラフ・チャート機能 | 棒グラフ・円グラフ・ヒートマップなどでデータを視覚的にわかりやすく表示 |
| アラート機能 | 基準値の変化や異常値を検知し、通知で即時対応を促す |
| ドリルダウン機能 | 全体データから地域別・商品別など詳細情報を掘り下げて分析できる |
| ドリルスルー機能 | グラフや数値をクリックして関連レポートや詳細情報に直接アクセスできる |
ダッシュボードの作り方6つのステップ
ダッシュボードを作成するときには、以下の6つのステップで進めます。
- 要件を定義する
- ダッシュボードを設計する
- データを収集する
- ダッシュボードを構築する
- 試験運用をする
- 公開・運用する
それぞれ、詳しく解説していきます。
要件を定義する
ダッシュボードの作り方の1つ目は、要件定義です。誰が・どのような目的で使用するのかを明確にし、得たい結果と必要なデータを洗い出します。たとえば、経営層が使うのか現場担当者なのかで、必要な情報や視点は異なります。
利用者や部署、目的が定まったら、最終目標と中間目標、具体的なアクションプランといった指標を設定しましょう。要件を明確にすることで、成果に直結するデータを的確に可視化するダッシュボードが設計できます。
ダッシュボードを設計する
ダッシュボードの作り方の2つ目は、ダッシュボードの設計です。情報を詰め込みすぎたり、過度な色や装飾を使ったりすると視認性が下がるため、シンプルで整ったデザインが効果的です。
内容に応じて棒グラフや円グラフ、ヒートマップなど適切なチャートを選ぶことで、データの伝わりやすさが向上します。また、ユーザーが必要な情報に素早くアクセスできるよう、フィルタリングやドリルダウンなどのインタラクティブな機能も設計に取り入れると、より実用的なダッシュボードになるでしょう。
データを収集する
ダッシュボードの作り方の3つ目は、データを収集することです。表示したいグラフや表が決まったら、どのデータをどのように組み合わせれば正確に表示できるかを整理します。たとえば「店舗別・月別の売上推移」を表示するには、日付、店舗名、売上額といった複数のデータが必要です。
また、売上の定義(税や手数料を含むかなど)も明確にしておく必要があります。こうした要件を整理したうえで、CRMやMAツール、DWHなど信頼性の高いデータソースから情報を収集し、分析に適した形で整えていきましょう。
ダッシュボードを構築する
ダッシュボードの作り方の4つ目は、ダッシュボードを構築することです。日々の業務判断に活用する場合は、データを自動で更新できる仕組みにしておくと利便性が高まります。ただし、使用するツールによっては自動更新に対応していない場合もあります。
その場合は「誰が・いつ・どのように」手動で更新するかを事前に決めておくことが大切です。更新頻度は日次が一般的で、始業前に前日分のデータが反映されている状態が理想的です。リアルタイム性が求められる場合は、数時間ごとの更新も検討しましょう。
試験運用をする
ダッシュボードの作り方の5つ目は、試験運用です。使いやすさや表示内容の妥当性を確認し、必要に応じてレイアウトや指標、機能を見直しましょう。
また、運用開始後もKPIの変更や情報ニーズの変化に対応できるよう、定期的にメンテナンスをする必要があります。修正を行う担当者と更新頻度を事前に決めておくことで、ダッシュボードの品質を維持できるでしょう。
公開・運用する
ダッシュボードの作り方の6つ目は、公開・運用することです。公開前には、閲覧権限やアクセス範囲を明確にし、必要なユーザーに適切な情報が届くよう設定します。
また、ダッシュボードの使い方や見るべき指標を関係者に共有し、正しく活用されるようサポート体制を整えることも重要です。運用開始後は、定期的に利用状況やデータの正確性を確認しながら、業務に即した形で継続的に改善を加えていくことが大切です。
ダッシュボードを作るときの4つのコツ
ダッシュボードを作るときには、以下の4つのコツを押さえましょう。
- 目標と指標を明確にする
- データの正確性を担保する
- 使いやすいUIにする
- セキュリティ対策をする
1つずつ、解説していきます。
目標と指標を明確にする
ダッシュボードを作るときのコツの1つ目は、目標と指標を明確にすることです。ダッシュボードは、情報を見やすくするだけでなく、意思決定や行動につなげるためのツールです。そのため、まずは何を達成したいのかという目的や目標を明確にし、それに紐づくKPIや中間指標を設定することが重要です。
目標が曖昧なままだと、データの選定や設計がぶれてしまい、使いにくいダッシュボードになってしまいます。目的に直結した指標を定め、効果的な可視化を実現しましょう。
データの正確性を担保する
ダッシュボードを作るときのコツの2つ目は、データの正確性を担保することです。どれだけ見やすく設計されていても、元のデータが誤っていれば正しい判断にはつながりません。
そのため、データの定義を明確にし、情報源を統一していきます。また、重複や欠損、集計ミスがないかを確認することも大切です。定期的に正確性をチェックする体制を整えておきましょう。信頼できるデータをもとに構築することで、ダッシュボードの信頼性と活用価値が高まります。
使いやすいUIにする
ダッシュボードを作るときのコツの3つ目は、使いやすいUIにすることです。情報が整理されていても、操作がわかりにくく見づらいダッシュボードでは、活用が進みません。
重要な情報は目立つ位置に配置し、過度な色や装飾は避けて、シンプルで直感的なレイアウトを意識しましょう。また、フィルターやドリルダウンなどの操作も、迷わず使えるよう設計することで、誰でもストレスなく活用できるダッシュボードになります。
セキュリティ対策をする
ダッシュボードを作るときのコツの4つ目は、セキュリティ対策をすることです。ダッシュボードには売上や顧客情報など機密性の高いデータが含まれることが多いため、不正アクセスや情報漏えいを防ぐ対策が欠かせません。
閲覧権限を設定し、必要な人だけが適切な情報にアクセスできるようにするのも方法の1つです。また、パスワード管理や通信の暗号化、アクセスログの記録なども重要です。安全に運用することで、安心して活用できるダッシュボードが実現します。
まとめ
ダッシュボードは、業務の可視化や意思決定のスピードアップに欠かせないツールです。また、作成時には明確な目標を定め、データの正確性を担保することも大切です。本記事で紹介したポイントを意識することで、使いやすく信頼性の高いダッシュボードが作成できます。社内のデータ活用を促進する第一歩として、ダッシュボード作成に取り組みましょう。